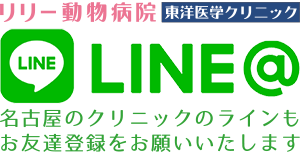ちょっとしたお話
本格的な暑さになって参りました。飼い主さん共々、ワンちゃん、猫ちゃんたちは夏バテ大丈夫ですか??
今回はこんな季節には特に多い病気、外耳炎のお話です。
外耳炎というのは、簡単にいえば耳の穴に炎症がおこる病気です。
原因はいろいろありますが、外耳道に蓄積した耳垢に、細菌やカビ、酵母が繁殖して、耳道の粘膜に感染が起こるのが一般的です。
特にこの暑い季節はお耳の中の環境が悪くなりやすいので、菌が増殖するにはもってこいの状態になってしまいがちです。
特にお耳が垂れているコや耳の中に毛が生えているコは、耳の中への通気性が悪いので、外耳炎になりやすい傾向があります。
その他にも外耳炎は、耳ダニというダニが耳の中に寄生することによって起こるものや、アレルギーの症状のひとつとして起こるものもあります。
- ・耳の汚れがひどい
- ・耳を引っかく
- ・頭をしきりに振る
- ・耳がにおう
- ・首を傾けている
などなどです。
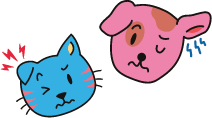
もしおうちのワンちゃん猫ちゃんにこのような症状が見られたら、外耳炎の可能性が高いです。
外耳炎の治療としてはまず原因を突き止めて、主にお耳のケアと点耳薬による治療を行います。
症状によって飲み薬を併用することもあります。アレルギーによるものが疑われる場合は、食事の変更や、アレルギー検査を行うこともあります。
外耳炎は進行してしまうと、炎症で壁が肥厚して耳の穴をふさいでしまったり、さらに奥に進行して中耳炎や内耳炎にまでなってしまう可能性もあるので、要注意です。
症状が見られたら、その段階ですぐ病院に連れて行って、炎症が軽い段階で治療を受けられることをお勧めします。
前々回で、「子宮蓄膿症」について触れましたので、今回は主に犬と猫の女の子の避妊手術の意味や、術後のメリットとデメリットについて簡単にご説明しますね。

1.避妊手術の目的
避妊手術の目的は、永久的な避妊の他、生殖器(卵巣、子宮、膣・・・代表的なのが、子宮蓄膿症)の病気の予防と治療、そして雌性ホルモンが関与していると思われる病気(乳腺腫瘍や肛門嚢腺腫など)の予防にあります。
避妊手術をする時期は、その動物の種類により性成熟(大人の身体になる時期)も異なるので一概には言えませんが、犬では6~15ヶ月、猫では6~9ヶ月で性成熟を迎えると考えたら、これより早期の時期が理想的だと言われています。(その理由は後述)
あまりにも早すぎる避妊手術は、麻酔の危険性もありますし、老齢であれば見かけは元気に見えても、循環器系、呼吸器系、その他の病気を考慮して、慎重に行わなければなりません。
2.避妊手術の時期と乳腺腫瘍との関係
乳腺腫瘍の発症は、避妊手術をする時期と大きく関連しています。
・犬の場合・・・初回発情以前,二回目の発情以前,二回目以降に避妊手術を行った場合の乳腺腫瘍の発症率は、それぞれ 0.05%,8%,26% だと言われています。
その後発情(年齢)を重ねていく毎に、乳腺腫瘍の発症率は増加しており、2歳半以降になると乳腺腫瘍の予防的効果はかなりの率で落ちるという報告があります。
・猫では同様に、6ヶ月以前,7~12ヶ月齢,13~24ヶ月齢時に避妊手術を行った乳腺腫瘍の発症率は、それぞれ9%,14%,89%であり、24ヶ月以降は殆ど無効であり、避妊していない猫は、避妊している猫の7倍乳腺腫瘍のリスクが高いと言う報告もあります。
(因みに、猫の乳腺腫瘍の80以上は悪性だと言われています。)
以上の事から、乳腺腫瘍の発症には性ホルモンが大きく関与しているので、性ホルモンの暴露の時期が短ければ短いほど、乳腺腫瘍の発症が抑えられると言えます。
3.子宮蓄膿症に関しては、どんな病気であったかは、前々回の「ちょっとしたお話」を参考にしてくださいね。
4.避妊手術のメリット
2・3などの病気を予防できる事の他に、発情期のマーキングや発情期の鳴き声(猫)、そして発情期の不安行動(例えば、飼い主さまや同居動物を咬んだりする行為)がなくなったりします。
5.避妊手術のデメリット
避妊手術によって、食欲抑制効果のあるエストロジェン(性ホルモン)の分泌が止まるので、術後、食欲増進によって肥満になる事があります。
それと共に卵巣を除去したことにより、生体に必要なカロリーが15~25%減少するため、手術前と同じカロリーの餌を与えていると、やはり肥満になり易いと言われています。
そして、術後の合併症として、卵巣の取り残しによる発情や子宮蓄膿症、そして尿失禁になる事もあると言われています。
また、東洋医学的観点から言うと、体の中心線である大事な任脈(にんみゃく)にメスで傷を付けることは、あまり良くないと言われており、高齢になってから、冷え性になる動物も弱冠ですがいるようです。
以上、避妊手術の概要を説明させて頂きました。
「病気ではない健康な動物に麻酔をかけて、避妊手術するのはある意味可哀想だ。」と言うお気持ちも「本当にそうだな~・・・。」と、思います。
ただ、今は20年や30年前とは違い、動物のワクチンやフィラリアの予防が徹底してきて、動物の寿命が長くなった分、上の2や3の病気も増えつつあると思います。
天寿をまっとうするまでの間、これらの病気にならなければ、これに越した事はないのですけどね・・・・。
ですので、これらの事を考慮して、未病と言う観点から若いうちに避妊手術をするか、どの動物も上の病気に罹るとは言い切れないから流れに任せるか・・・とても難しい選択だと思いますが、やはりこれらの病気になった動物達を治療させて頂く立場の私としては、最終的には、避妊手術をお薦めしたいと思います。
後は、動物達は口が利けませんので、飼い主さまの判断ですね・・・。。。
 暑い季節がやってきました。この時期、草むらで活動的になる要注意な生き物達がいます。
暑い季節がやってきました。この時期、草むらで活動的になる要注意な生き物達がいます。
今回は好奇心旺盛なワンちゃん猫ちゃんには要注意な、そんな生き物達についてご紹介したいと思います。
- ■マムシ
-
頭が三角形で胴が短いのが特徴のヘビです。
咬まれた場合、すぐ激痛とともに局所がひどく腫れます。皮下出血や嘔吐、呼吸困難をおこすこともあります。
ちょうど先日、耳を咬まれて治療をしたワンちゃんがいました。
- ■ヤマカガシ
-
全長80センチくらいの日本で一番多い毒ヘビです。
毒牙で咬まれると血液の凝固障害や皮下出血、臓器不全などがおこります。体をおさえるとウロコの間からも毒液を出します。
- ■カエル
-
耳の後ろにある耳腺から毒液を出すカエルがいます。
また、ヒキガエルの全身のイボからは「ガマの油」として知られている白い毒液がにじみ出ていて、嘔吐や視力障害、神経障害などを起こします。
これも先日、散歩中にカエルで遊んでいたあるワンちゃんがお目眼をやられてしまって、飼い主さんがすぐに眼を洗浄したことで難を逃れました。
- ■ムカデ
-
肉食で、触るとすぐに咬む、ゲジゲジした生き物です。
咬まれたときの主な症状は局所の激しい痛みと腫れで、全身症状が出ることはあまりありません。
よく外で干している洗濯物についていることがあるので、要注意です‥!
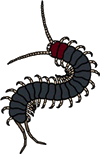
- ■ニホンイモリ
-
別名アカハライモリで、お腹が赤いのが特徴的なイモリです。
皮膚にフグと同じテトロドトキシンという毒を持ちます。
これらの生き物達にやられてしまった時は、傷口や眼に毒が入ったと思われる時はすぐに水で洗浄してあげて、そのまま動物病院に連れてきてください。
もちろんワンちゃん猫ちゃんだけでなく人にとっても要注意な生き物達なので、特に草むらや田んぼ道を歩かれる時には、気をつけてくださいね。
2008/6/21掲載
追伸—
ヘビにかまれた疑いで来院したワンちゃん猫ちゃんは今年だけで、すでに5匹以上です‥!
みなさん、気をつけてくださいね。
2008/7/28追加掲載
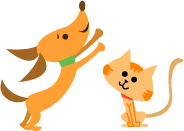 健康だった中年以降(大体4~5歳以上と考えて頂いて良いと思います。)のメスの犬や猫が突然、嘔吐が始まったり元気がなくなったりして、血液検査やレントゲン、超音波検査で、子宮蓄膿症だと診断される事があります。
健康だった中年以降(大体4~5歳以上と考えて頂いて良いと思います。)のメスの犬や猫が突然、嘔吐が始まったり元気がなくなったりして、血液検査やレントゲン、超音波検査で、子宮蓄膿症だと診断される事があります。
子宮蓄膿症は、中年以降の避妊手術をしていないメス犬(猫)に発症する病気です。
犬では、平均発症年齢は7・1プラスマイナス2.4歳であり、自然発症率は0.6%と言われていますが、9歳以上の未避妊犬の発症率は66%と言う報告があります。
症状は、元気及び食欲の低下、多飲、多尿、嘔吐、腹部膨満、陰部からの膿の排出(これを開放型と言い、陰部から膿が排出されない型を閉鎖型と言います。)などです。
放置すると、腎機能不全やDIC(=藩種性血管内凝固症候群 後述※①)によって死に至る事もあります。
子宮蓄膿症は、性ホルモン(エストロジェンの刺激やプロジェストロン)が多く関与しており、それと共に細菌感染(原因菌の70%は大腸菌)が起こる事により、発症します。
治療法は、内科的療法(プロスタグランジンF2アルファーと言うホルモン剤の注射)で抑える事も出来ますが、20%前後で再発があると言われています。
ですので、完全なる治療法は、出来るだけ早期に卵巣と子宮の摘出をするのが一番だと思われます。
尚、早期に手術を行っても、先程言いましたDICや免疫異常による自己免疫性溶血性貧血(後述※②)などを併発し、2~3%(他の資料では、5~8%)の動物が死亡すると言う報告があります。
それなりの年齢のメスの犬猫を飼ってらして、以上の症状を示し、尚且つ未避妊であった場合、子宮蓄膿症の疑いがありますので、早めに受診される事をお勧めします。
(因みに・・・犬猫と書いてきましたが、これは犬猫に限った事ではなく、兎やフェレットなどでも発症します。)
※①DIC(藩種性血管内凝固症候群)
いわゆる血液の凝固疾患のことであります。様々な疾患によって組織障害が起こり、その為に血管凝固促進物質が大量に流出して、凝固系の働きが更新します。その為に血小板やフィブリノーゲンなどの凝固因子が大量に使われ、そして不足し、その結果凝固異常を起すもので、血栓による循環障害、ショック、出血などが起こる状態のことです。
※②自己免疫性溶血性貧血
細菌感染などの他、あらゆる原因により免疫異常がおこり、自分自身の赤血球を標的にしてしまい、その免疫反応の結果貧血になる病態を言います。
酷暑に多かった皮膚病も治まり、その後少しの間、消化器病(下痢や嘔吐)が流行りましたが、昼夜の寒暖の差が激しいこの10月は泌尿器病や循環器病が目立つように思います。
今日は泌尿器病についてお話しさせて頂きますね。
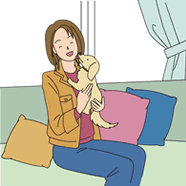 当院に来院される泌尿器病で一番多いのが、膀胱結石(結石になる前の結晶の状態の子が多いですが。)です。
当院に来院される泌尿器病で一番多いのが、膀胱結石(結石になる前の結晶の状態の子が多いですが。)です。
結石の種類は、ストルバイトが圧倒的に多い様に思いますが、その他にもシュウ酸カルシウムや尿酸アンモニウム、システィン(稀です)などがあります。
その原因は、体質(生成され易い体質、特に犬はよく発症する結石が特定の犬種で認められる事から、代謝障害などは遺伝するのではないかと言われています。)、細菌・ウィルス感染、ストレスなどが考えられます。
一旦治療させて頂いて、尿中の結晶が検査で認められなくなっても、月に一度はおしっこの検査をさせて頂いています。
初発で認められる症状は、排尿困難、排尿痛、頻尿、血尿などです。
以上の症状は、膀胱結石以外に、単純な膀胱炎(結石と併発することは多々ありますが。)や、腎疾患、泌尿器の腫瘍、そして♂犬でしたら、前立腺肥大など、様々な原因によっても起こります。
原因により治療は異なってきますが、長い間放置しておくと、やはり治癒に時間が掛かる事が多いので、お家でお飼いになっている動物達のおしっこの回数が増えていたり、色が変わっていたりその他諸々の症状がありましたら、一度受診されることをお勧めします。。
 フィラリアの予防薬は、蚊が吸血中に犬猫の体内に蚊のお腹からフィラリアを入れてから一ヶ月間成長したフィラリアの子虫(まだ成虫になる前の段階で)を駆虫するものです。
フィラリアの予防薬は、蚊が吸血中に犬猫の体内に蚊のお腹からフィラリアを入れてから一ヶ月間成長したフィラリアの子虫(まだ成虫になる前の段階で)を駆虫するものです。
そろそろ涼しくなり蚊の量も減って来ましたが、薬の性質上、一月前にさかのぼって考えて予防しなくてはなりません。
ですので、蚊が出始めて一ヶ月してから予防を開始し、蚊があまり飛ばなくなってから一ヵ月後に予防を終ることになります。
かの有名な忠犬ハチ公は、東京大学で解剖した結果、実はフィラリアに侵されて死んだのだと言われています。(これは余談ですね・・・。)
私の臨床の経験でも、外飼いの犬で、1シーズン(ひと夏)のうちの数ヶ月間、飼い主さんがフィラリアの予防をし忘れただけで、次の年に心臓の聴診をしたら、心臓の音が変わっていた(フィラリア独特の心臓の不整脈)ことが結構あります。
ご自分のワンコちゃんの心臓がフィラリアに侵される事なく、いつもきれいなままの心臓である為にも、最後まできちんと予防して下さいね。
これは飼い主さんの責任ですので、どうぞよろしくお願い致します。
毎年この時期(四月下旬の田植えが始まりつつある時期から九月下旬頃まで)になると、除草剤を撒く方がでてきて、お散歩中のわんちゃんが中毒になり、病院に運ばれてくる事があります。
軽症では、一過性の嘔吐などの消化器症状で済むのですが、重症になると、吐血、そして肝臓障害、腎臓障害など、多臓器に渡る障害を受け、命を落とす子達もいます。
 除草剤は、散布した直後は解らない為、わんちゃんも(そして飼い主さんも)それに気付かずに、食べて(食べさせて)しまいます。
除草剤は、散布した直後は解らない為、わんちゃんも(そして飼い主さんも)それに気付かずに、食べて(食べさせて)しまいます。
犬が(猫も)、先の尖った草を食すのは、体が繊維を求めていたり、少し胃などの消化器がむかついたりする時だと言われており、その行為自体は異常ではないのですが、これからの時期は、除草剤による中毒にならない様、くれぐれもお気をつけ下さい。
そして、草を食べた後、異変を感じたら、直ぐに受診して下さいね。
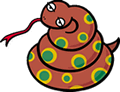 好奇心旺盛なワンちゃん、猫ちゃん達はお散歩で、たまに蜂や蛇の害に遭うことがあります。
好奇心旺盛なワンちゃん、猫ちゃん達はお散歩で、たまに蜂や蛇の害に遭うことがあります。
それらに刺されたり、咬まれた場合、以下の事を参考にして頂ければと思います。
●蜂について
毒を持つ蜂として一般的なのが、スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、クマバチです。
ミツバチとクマバチの針にはトゲがついており、刺さった部分に残りますが、スズメバチとアシナガバチは何度でも刺します。
ハチの毒はアナフィラキシーショック(急性のアレルギー反応)を起こす事がありますので、一刻も早い治療が必要です。
応急処置としては、針が残っている場合は抜き取ります。但し、針には毒嚢という透明の袋が付いてますから、摘んで毒を押し込んでしまわないように、爪で弾き飛ばすようにするのが良いと言われています。
吸引器具があれば、毒を吸出し、水でよく洗い流します。(蜂の毒は水に溶けます。)
抗ヒスタミン薬やステロイドの軟膏があれば、塗って冷やしておきます。
応急処置の後は、直ぐ近くの病院へ連れて行ってください。
●ムカデについて
ムカデは肉食で、触ると直ぐに咬みます。夜行性の為、咬傷はたいてい夜に起こります。
主な症状は局所の激しい痛みと腫れで、全身症状が起こることはあまりありません。
抗ヒスタミン薬やステロイドの軟膏を塗り、局所を冷やした後、病院へ連れて行ってください。
●ヘビ(マムシ、ヤマカガシ)について
マムシに咬まれた場合、直ぐ激痛とともに局所がひどく腫れ始めます。
腫れは急速に広がり、皮下出血や筋肉の壊死、嘔吐、呼吸困難、DIC(播種性血管内凝固症候群)、腎不全などを惹き起こすこともあります。
顔面を咬まれた場合は、患部からいつまでも出血していることがあります。
四肢を咬まれた場合は、命にかかわる事は殆どありませんが、治療が遅れると重症になります。
マムシ、もしくはそれ以外の毒ヘビに咬まれた場合、患部を縛ったり、切開したり、冷やしたりという処置は、方法を誤ると却って悪化させる場合にもなりかねません。出来るだけ早く、病院に連れて行く事が大切です。
尚、ヤマカガシなど、体の毒腺から毒液を噴出して、それが目に入ると重度の眼症状が起こることがあるので、その場で直ぐに、大量の水で洗い流してから病院に連れて行ってください。
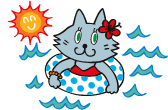
●膿皮症とは
温度・湿度の高い梅雨から夏にかけてよく見られる病気の一つとして「膿皮症(のうひしょう)」という病気があります。この病気になると、皮膚の表面や毛穴の部分がポツポツと赤くなったり、膨らんだりします。かゆみの為、なめたり掻いたりする仕草もみられます。
●膿皮症の原因は?
この原因は細菌(主に黄色ブドウ球菌)の感染によるものです。
膿皮症は気候やストレスなどの何らかの理由によって皮膚の免疫力・抵抗力が低下し、通常の状態よりも細菌が異常に増殖してしまっている状態です。
●予防法
 皮膚を清潔に、乾燥させておく事が予防につながります。ただし、シャンプーのしすぎも皮膚の抵抗力を低下させることがあります。間隔は3~4週間に一度くらいがベストでしょう。
皮膚を清潔に、乾燥させておく事が予防につながります。ただし、シャンプーのしすぎも皮膚の抵抗力を低下させることがあります。間隔は3~4週間に一度くらいがベストでしょう。
また、長毛種の子は夏場だけでも短く毛をカットしてしまうのも良いでしょう。汚れがつきにくい、毛玉の防止、湿気がこもりにくいなどのメリットがあります。
それでも膿皮症になってしまった場合は治療が必要になります。気になる症状がある場合は病院で診察をうけてみてください。
 猫さんも、人間と同じように風邪のような症状を示すことがあります。
猫さんも、人間と同じように風邪のような症状を示すことがあります。
症状としては、激しいくしゃみや咳をし、たくさん鼻水を飛ばしたり、目やにが出たりします。
これは猫ヘルペスウイルスによって起こる病気で、「猫ウイルス性鼻気管炎」といいます。40度前後の発熱があり、のども腫れますので、元気や食欲がなくなる猫さんもいます。
強い伝染力があり、他のウイルスや細菌との混合感染を引き起こし、症状が重い場合は死亡することもあります。特に子猫はかかりやすく、目や鼻に後遺症を残したり、高い死亡率を示す場合があります。
●猫の風邪は人間にもうつるの?
飼い主さんからときどき質問を受けますが、猫さんの風邪は人間には感染しません。逆に、人間の風邪が猫さんに感染することもありませんので、安心していっしょに生活できます。
●「猫ウイルス性鼻気管炎」にならないためにはどうしたらいいの?
感染してしまってから治療するには時間がかかり、その間飼い主さんも猫さんもつらい思いをします。
「猫ウイルス性鼻気管炎」にはワクチンがあり、予防することができます。万が一感染してしまった場合も、症状が軽くすみます。
大事な猫さんが健康に過ごすために、ワクチンの接種はとても重要です。
猫のワクチンは、他の怖い伝染病との混合ワクチンになっていますので、予防のために、ぜひ定期的なワクチンをおすすめします。